『セイバーマリオネット』あかほりさとる、『ロードス島戦記』水野良 レジェンドラノベ作家にぶっちゃけ話(真剣)をしてもらった! 「ファンタジーは書いたらダメ」「(初版7万部でも)売れないからやめましょう」と言われた時代
ラノベ文体の始祖は、まさかの……
──あかほり先生はデビュー前からロードスをお読みでしたが、水野先生はあかほり先生の作品を読んでいらしたんですか?
水野:
一応、どんなもんかとチェックはしていましたよ。で、読んで「すごいなー」と。
あかほり:
15分で読めるって有名だったからね。
──そう! それも発明だなって思うんですよ。読みやすいからこそ低年齢層にまで届いた。1冊通して本が読めるって、子供にとってすごく大きな自信になるので。
水野:
あれはスタイルだよね。
──最初の読書体験があかほり作品だった人って、多かったですもん。あの文体はやはり発明で、それがあったからこそラノベがここまで流行したんだと思います。
あかほり:
けどね? 当時、白鳥君たちが書いてるみたいな作品ばかりだったら、俺はそもそもラノベを書いてなかったと思うんだ。きっと本を書こうなんて思わなかった。今はそれくらいしっかりした作品が多いし。
黎明期のスニーカー文庫って……すごいのもあったけど、俺から見ても「ええ~……?」ってのもいっぱいあってさ。だから俺なんかでも行けたんだけど。
水野:
初期のメンバーって、それまでプロの作家としてやっておられた方々もいらっしゃったけど……。
あかほり:
実験作もいっぱいあったしね!
水野:
うん。あとは、アニメの脚本家の方もいらっしゃったかな?
あかほり:
そうね。富田祐弘さんは『ガルフォース』のノベライズを書いてたかな。
──富田先生はオリジナルもあって、富士見で『ペ天使たち』シリーズと、スニーカーで『D.A.ジャンクション』シリーズを書いていらっしゃいましたね。鈴木雅久さんのイラスト、好きだったなぁ。あとはSFからいらっしゃった方も多い印象です。
水野:
もともとスニーカー文庫を角川が始めるまで、ラノベといわれるようなものを出してたのってソノラマじゃないですか。ソノラマはSF系が多かったよね。
──富野監督の小説版『ガンダム』シリーズも最初はソノラマでしたね。
水野:
菊地秀行さんとか、夢枕獏さんとか。あと新井素子さんは……コバルトか。
──ラノベの文体の特徴として、会話が多いということは挙げられると思うんです。会話だけでも内容が伝わるというか、会話劇であることは間違いない。そこが読みやすさに繋がっていると思うんですが、あかほり先生は意識して書いていらっしゃったんですか?
あかほり:
会話……っていうか、リズムでしょ。
──リズム。
あかほり:
ライトノベルのリズムって……何か、早いよね? それは作品を読むスピードというか……たとえば純文学と比べると、ラノベって文章が頭の中に入っていく速度が早いと思うんだよね。
──わかる……気がします。『内容がスルスル頭に入ってくる』は、中学高校時代にあかほり先生のラノベを読んでた人間がみんな言ってましたから。
あかほり:
逆に、今のラノベはリズムが遅くなったような気がする。俺と同じような文体をしてる作品は今も多いのかもしれないけど……昔の作品は、もっと早かった気がするんだ。
──文字数とか、改行とか、そういう部分だけでは真似できない技術があった。確かに……。
水野:
それはリズムが悪いんだろうね。文章の。
あかほり:
悪いっつうか……音楽にもロックとかフォークとかあるじゃん? 昔はもっとテンポが早かったんだろうけど、今はゆっくりになったのかもしれないね。同じ会話劇なのかもしれないけど。

──水野先生はご自身の作品がラノベであって純文学ではないという説明をなさる際に「頭の中で二次元のキャラクターを動かして書いているからだ」とおっしゃるじゃないですか。
水野:
ああ、言いますね。
──実在の人間じゃなくて、アニメのキャラクターだと。それって重要だと思っていて……あかほり先生もアニメの脚本家だから、キャラに命を吹き込むための文章じゃないですか。お2人ともアニメのキャラクターを動かしているという共通点があって、そこが文体は違っていてもラノベを結びつける要素なのかなと。
水野:
うん。キャラクターというか、イラストあってのものというのはあるんじゃないですか。
でもね? 会話中心に書いてても、軽い文体じゃない。それはできるんです。夢枕獏さんがそうだから。
獏先生がメチャメチャ忙しい頃に……改行がすごく多い時期があったんですよ。『キマイラ』とかね。
あかほり:
はっはっは!
──あっ!『餓狼伝』とかですか?
水野:
そう。「九十九は○○であった。ごつい。」「風が鳴る。ヒョウ。」とか。
──その短い単語ごと改行してあるんですよね。
水野:
散文的なんですよ。散文もお得意な方なので。
あかほり:
俺は夢枕獏さんの文体、めっちゃ参考にしたぜ。
水野:
僕も! すごく好きで。
あかほり:
最初に文章を書くことになって「どうしようかな?」って迷ったんだけど、菊地先生というよりは夢枕獏さんだな、と思って。
──そうなんですか!?
水野:
あのね。「○○であった」って書きたくなるんですよ!
あかほり:
でもね、これが難しいんだ! 全然ダメだった(笑)。
水野:
真似はできるんですよ。でもそれって獏先生の亜流にしかならない。
──当時は文庫よりも新書タイプのノベルズがすごく強い時代でしたから、みなさんそこに憧れがあったんでしょうか?
水野:
そうですねぇ……やはり獏先生のあの文体と、田中芳樹先生のキャラ描写の見事さ。短い文章でキャラクター性を獲得させるのは「神だなこの人たちは!」と思いましたね。
あかほり:
いやー……これはちょっと言いたくないんだけど、『シュラト』に関しては俺が書くはずじゃなかったのよ。
──ええ!?
あかほり:
当時、俺はタツノコの人間で。営業的なものもやらされていたから。それで知り合いのエニックスの人に営業をかけて、本を出すことになったんだけど……書くのは当然、脚本家だと思ってたの。
──あ! そうか。あかほり先生は設定などを考える文芸担当で、脚本は師匠の小山先生が書いていらっしゃったんでしたね。
あかほり:
そしたら脚本家が「誰も書かない」と。それで俺が急遽、書くことになっちゃった。で、切羽詰まって「文体どうすりゃいいんだ!?」と悩んで……好きな夢枕先生を真似て「こんなんでいいかな?」と書いたら、全然そうはならなかったと(笑)。
水野:
ははははは!
──けど、言われてみれば……あかほり先生の文体って、夢枕先生の文体に似てますね。伝奇小説とラブコメでジャンルが違いすぎるから共通点に気付かなかったけど……そうか。そこに源流があったのか……。てっきり私は、アニメの脚本はセリフ中心だから、そのせいかと思っていました。
あかほり:
ノベライズだからシナリオをまとめながら書いていくんだけど、シナリオなんてほぼセリフしか書いてないわけだから。全然ためにならない。夢枕先生の『餓狼伝』や『サイコダイバー』といった、大好きだった作品を必死に勉強して……。
──特に『シュラト』は冒頭に拳法大会のシーンがあったり、精神世界的な描写も多いですもんね。作風的にも夢枕先生に近い。
水野:
(被せるように)『サイコダイバー』はすごいですよ! あれは、漫画やアニメといった映像作品がエンタメ界の主流になっていく時代に、小説という表現が生き残っていける確信を与えてくれました。
むっちゃ感動して! 小説が他のメディアに負けないなと思うのは、これだな! と思ってたんですよ!
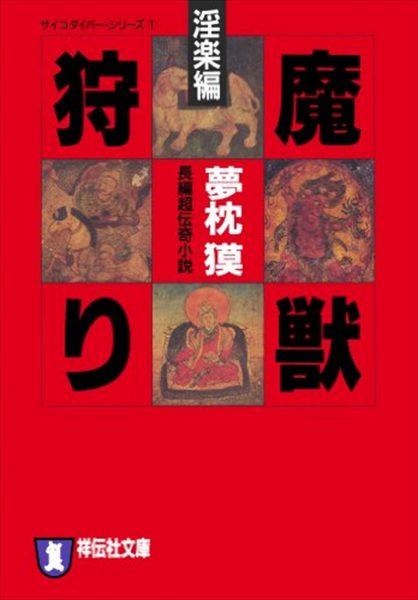
あかほり:
とにかく、初期の頃のことは思い出したくないよね。インスパイアといえば聞こえはいいけど、今はトレースをすると叩かれる時代だから(笑)。
水野:
けどさ。西尾維新【※】さんのトレースなんて山ほどいたじゃん。
※西尾維新……『〈物語〉シリーズ』『刀語』作者。
──いましたねぇ……まさに私の世代はそればっかでした。
水野:
西尾維新さんも文体を確立された方じゃないですか。それこそ僕らの時代だと、新井素子さんがそうだった。
そして文体のリズム感だと、神坂さんが抜群に上手い。あと、文章が上手いのは『オーフェン』の秋田さん【※】。
※秋田禎信……『魔術士オーフェン』シリーズ作者。
あかほり:
神坂さんこそさぁ、一人称文体とはいえ、あのリズム感がラノベだよね!「ラノベって何?」って質問に対しては『スレイヤーズ』を読ませるのが一番だと思うな。
──少し前に新刊も出ましたしね!
お家騒動とラノベ三国志
──ラノベの発展にとって、レーベルの存在は欠かせません。スニーカー、富士見、電撃……それぞれレーベルカラーといえるものがありました。先生方は複数のレーベルで作品を発表してこられましたが、レーベルごとに作風を変えるというようなことはなさったんですか? それこそ、スニーカーも富士見も電撃も立ち上げから関わっていらっしゃったと思うのですが。
あかほり:
いや? 無いなぁ。
水野:
作品ごとに文体を変えるというようなことはしましたかね。
──水野先生はその印象が強いですよね。それこそリウイはハーレムですし、それに電撃文庫の『クリスタニア』は、ロードスの1巻に、かなり意識して寄せているような感じを受けます。
水野:
そもそもクリスタニアを書き始めた理由が……お家騒動みたいな、ねぇ?
あかほり:
がはははは!
──それ書いていいんですか!?
水野:
もう情報公開されてるからね。角川の社史にも出てるし。あれには僕の名前もいっぱい出していただいてるみたいだけど。
──佐藤辰男さんがお書きになった『KADOKAWAのメディアミックス全史 サブカルチャーの創造と発展』ですね。ちなみに佐藤さんはコンプティーク創刊時の編集長でもあり、ロードス誕生やラノベ発展の歴史にも深く関わっています。あのお家騒動では角川歴彦さんと行動を共にされました。水野先生も、やはり当時は色々と……?
水野:
やっぱり……渦中だったからね。中心人物ではないですけど、その近くにいる人ではあったから。そりゃあ警戒しましたよ。
神戸に角川歴彦さんが来られたときも、安田さんと……かなり大人の話をしてるんですよ。で、僕もその隣にいるんですけど……もう僕は話なんて聞いてないですよ! 周りに週刊誌や新聞の記者がいないかとか、そんなんばっか気にしてましたよ!
場所はホテルのラウンジでしたけど「この人ら……なんやぜんぜん警戒してへんなぁ!?」って。

あかほり:
ははは!
水野:
僕は歴史オタクなところがあるから、こういう密談は茶室でやるもんだろうと(笑)。そういう先入観があったから。
──当時、私はまだ小学生でしたけど、テレビで大ニュースになってたのは憶えています。そんな大きな話を、わりとオープンな場でしてたんですね……。
水野:
僕もいろいろと情報を仕入れてましたよ。僕は2流以下の策士なんで、そういう情報収集は怠らないんです。で、いくつかプランを用意しておいて……結局、クリスタニアを電撃文庫に持って行って。
ある意味、ロードスとクリスタニアを分けることで、根本的なトラブルを避けたということはありますね。
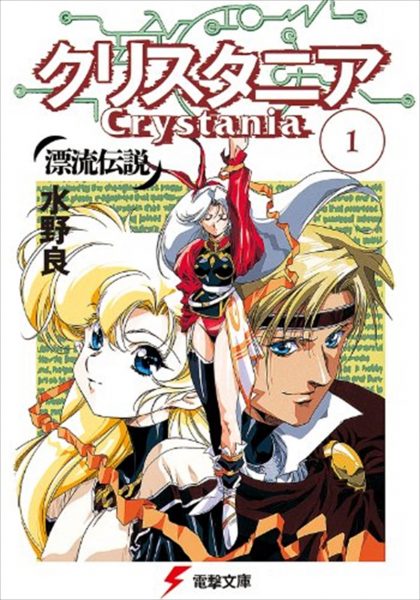
──なるほど。どっちが倒れてもいいと……。
水野:
真田か俺は!! そういうんじゃなくて(笑)。
あかほり:
でもね? 当時そういう雰囲気はあったよ。関ケ原で東軍に付くか西軍に付くかってさ。
水野さんはそうやって大人的にやってたけど……俺はもっと露骨にさぁ。一方には「もちろん僕はこっちですよぉ!」で、もう一方にも「もちろん僕はこっちですよぉ!」って(笑)。
水野:
筒井順慶か(笑)。
──離脱派の決起集会みたいなのがあったときに、あかほり先生がその場にいなかったのに、後からいたことにされたというエピソードが……。
あかほり:
そそそ! 決起集会というか、作家に対する説明会みたいなのがあったのね。俺は別の作品で外国に取材に行ってたんだけど……帰って来たら、いま角川の子会社で社長やってる横沢ってのがいて、これはずっと俺の担当をするんだけど、その横沢に 「あかほりさん。俺たち角川出て行くけど、あんたどうする?」って言われて。
そのころ『爆れつハンター』の原型みたいなものがあったんだけど……「もちろん行きますよ!」と言ったのは憶えてる(笑)。
──ちなみに『爆れつハンター』は出て行った方々が作った電撃文庫から無事に刊行されていますね(笑)。
あかほり:
そのあと、スニーカーとかドラゴンマガジンの編集部に行って「いろいろあるけど、これからもよろしくお願いします!」って言ったのも憶えてる(笑)。

──みなさん、そんな感じだったんですかね?
水野:
どっちに付くかってのは、みんなありましたよ。引っ張り合いもありましたしね。ただ、ファンにとっては関係のない話じゃないですか。
──ですね。スニーカーでやってたはずの作品が電撃文庫というところから出てて、けっこう戸惑ったおぼえがあります。「主婦の友社!? 角川じゃないの!?」って。しかも電撃は装丁が幼いというか、より漫画っぽくなったので、親が買ってくれなかったり。
水野:
だから僕は、ロードスを電撃に持って行くことは全く考えなかった。その代わり、クリスタニアで全力を尽くしますよと。日和見といえば日和見です。でも、ファンに対してはそれが普通だと思う。
あかほり:
その点、俺は楽だったよね。さっきも説明したけど、俺はスニーカー文庫でも、もともと角川の一般文芸をやってる編集さんたちと仕事してたから。
──あ! そうですよね。水野先生はロードスを担当していた人たちが角川から去ったから、板挟みになったわけで。
あかほり:
わかれる人たちとも仕事してたけど、別の作品をやってたから。だから自然と分け合う形になってたから(笑)。
それに角川さんともお付き合いがあったけど、その頃はもう別の出版社さんとも仕事してたからね。最悪は亡命だなと(笑)。
──それだけの大騒動がありましたが……とある事件をきっかけに、翌年にはもう歴彦会長が角川に戻るという……。
水野:
そう(苦笑)。
あかほり:
両方にいい顔しててよかったなーって。
水野:
僕もまさにそう思いましたよ(笑)。
やっぱりねぇ……現実というものは想像を超えるんだよ。
──フィクションは常に現実に負けるんですね(笑)。ただ、電撃のレーベルはそのまま続くことになります。
水野:
そこから三国志になるわけだよ。
あかほり:
その後まさかファミ通系を買収して、メディアファクトリーも買収するとは思わなかったぜ!
水野:
超帝国を築いたよね。角川がどんどん悪の帝国化していく(笑)。
──電子書籍の時代が来て、さらにそれが加速していますよね。我々のような周辺の異民族は、かろうじて生き残ってるような感じで……。
あかほり:
匈奴は強いからいいじゃん(笑)。
売れる、ということ
──ところで先生方は、作品を書く際に何を意識していらっしゃいました? 編集者なのか、同業者なのか、それとも他人のことは考えずに自分の書きたいものだけを書いてきたのか……。
あかほり:
これもさぁ……アニメの企画をやっちゃったからのデメリットというか……ホント、よくないことが起こって。
──最初に言いかけておられましたね。詳しく教えていただけませんか?
あかほり:
要は、企画をやるでしょ? そうすると、ものすごく……「相手が何をやりたいか」で始めちゃうの。結果、それを膨らませて「これどうですか?」って。今や企画屋? クリエーターってよりも、なんて言うのかな……ねぇ?
編集に近いのかな? アレンジャーなのかなぁ?
──過去のインタビューでは、『御用聞き』に近くなってしまったと自戒しておられましたが……。
あかほり:
これは当時俺が叩かれる理由にもなるんだけど……向こうが求めてるものが何かなってのがあるし。あとやっぱり「これ売れるかな?」って考えちゃった。露骨に考えちゃった。
──それは、たとえば「売れてるものに似せよう」みたいな?
あかほり:
いや。数字を意識してた。「これはどれだけ数字を取れるかな?」ってのが判断材料にすごく入ってた。
──なるほど。それは確かに「相手の求めるもの」の究極ですね。世間の求めるものですから。
あかほり:
自分のやりたいものをやって、それが当たるのが一番いいんだよ。売れなくても「いいものが作れたから、それでいい」という考えもあった。そういうことを言う時代でもあったんだ。「売れなくても、これはいいものだから」って。
でも、それじゃダメだと。退路を断たなくちゃいけないから。まずは「売れるか売れないか」。次に「売れたけどいいもの。売れたけどダメなもの」。そういうわけかたはいいけど「売れなかったけどいいもの」はダメだなと。

──『売れる』ということが、あかほりさとるの存在価値だった……と、先生は思っておられたんですね。
あかほり:
それをラジオとかで言っちゃったから、ファンからすごく叩かれた。はっはっは!「売らんかな」でやるなって!
水野:
いや! ラノベ作家の戦闘力って、結局は売れてる部数やから。「いま現在の売れてる部数」やから。
──肩書きが生きない世界ですからね。
あかほり:
そうだね。ラノベに文学賞とかあるわけじゃないからね。
──水野先生は何を意識して執筆していらっしゃいましたか?
水野:
やっぱり「売れる」ってことは意識しますよ。
特に僕は、書ける作品の量が多くないので。1つの作品にかけるカロリーも大きいから……世界設定から考えるから、どうしても1年くらいかかるわけですよ。最低でも。
そこでさらに熟成させていって……となるので。自分の書きたいものというのはもちろんあるんですけど、それをどういう形にすれば売れるのかという点で、知恵を使いますよ。いつも。
僕はいつも大ヒットを狙うので。常にミリオンを狙うので。「こうやれば化けるんちゃうか?」という幻想はいつも抱いてるんですけど(笑)。
あかほり:
(無言で拍手)

──しかも水野先生が基準にされるミリオンって、シリーズ100万部じゃなくて、1巻単巻で100万部ですもんね。
水野:
もちろん現実には、そんなものは夢物語だとはわかるんです。
けど僕はロードスで最初にそれをやってしまったから。だからそこを目指さないとロードス超えにはならないんですよ。
あかほり:
水野さんは1本をしっかりやるよね。俺は数打ちゃ当たるだから。
──ただ……1年かけて築き上げた世界設定が、1冊だけで終わってしまったら、元が取れないというか。
水野:
そんなことは仕方がないですよ。だから僕のやりかたの真似をしても、ええことは無いと思いますよ。
あかほり:
そんなことないでしょ……。
水野:
1巻が面白かったら続きを出してもらえるのは当たり前でしょ。同じように、つまらなかったら1巻だけで終わるのも当たり前じゃないですか。
僕はだから、1巻でダメだったら、そこでスパッと切っていただいて結構だと考えます。また1年間かけて別の作品を準備します!
──水野先生は様々な作品を書いておられます。そして私が読むに、明らかにそれぞれの作品の文体が違う。たとえばさっき話に出た『リウイ』は会話中心で改行も多い。
水野:
改行のペースは明らかにコントロールしていますね。
──『クリスタニア』はロードス島戦記に近くて、1ページ当たりの文字数も抑えめで、文体は三人称ですが視点は主人公のものが多い。ここから初めて水野作品に、そしてラノベというジャンルに触れる子供たちのことを意識していらっしゃるのかな……と。
水野:
よく読んでおられる。ただ、文体を変えているというほどの意識はなくて……僕は「リアリティーレベル」と呼んでいるんだけど。
──おっしゃってますね。それこそ、あかほり先生がファンタジーの話題でおっしゃっていた『枷』がそれに当たるのだと思いますが。
水野:
そこは意識して書いています。たとえば『ロードス島伝説』という作品は、「僕はここで重厚なファンタジーを書き切るのだ!」という強い意志を持って、自分がそれまで書いたことのないような重厚な文章にチャレンジしてみたんですよ。
で、ある程度成功したという感触もあった。だから伝説のおかげで、自分は小説家になれたかなという印象は持っていて。
『リウイ』では逆に、文体を軽くするということがやれた。その2つによって、文体のコントロールをやれるようになったと思います。
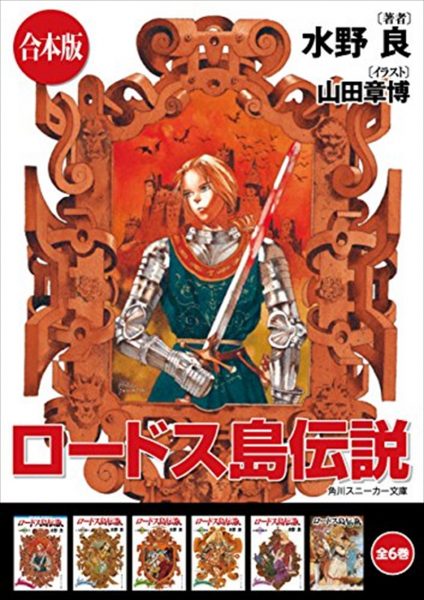
──あの、個人的な話で恐縮なんですが……私は同じ作品をずっとやってて。
水野:
ああ、はい。
──自分の文章力が上がっているという実感が無いんです。苦労や努力はしてるんですけど……それは一つの作品だけに取り組みすぎている弊害なんでしょうか? もっと色々な作品を書くことで、自分の芸域を広げる努力をしたほうが……。
水野:
いや、一つの作品を書いているなら、文章力を上げる必要はないでしょう。文体を変える必要もないし。
同じ作品をやってるなら、縮小再生産でいいと思うんです。なぜなら基本的に2巻以降、部数というのは下がっていくから。そこでどんだけ努力しても部数がバーッと跳ね上がることはない。
だからそこは再生産で、次に別の作品をやるときに努力や工夫をすればいい。まあ、白鳥さんのほうが、作家としての人生設計を僕よりもしっかり立ててるだろうから。
──あんまり立ててなかったんです。ずっと兼業でしたし。けど、結婚して専業になって、子供が生まれてしまうと「長くやらなきゃ」という気持ちが生まれてしまって……。
水野:
そうですよねぇ。僕は若い頃に勢いで結婚して、子供も生まれたから。もう育ってくれたんで、今は楽ですけど。
あかほり:
おいおいおい! そこの2人。俺も子供欲しいぞ!
──あかほり先生は、お弟子さんのお子さんをかわいがっておられるじゃないですか。
あかほり:
おじいちゃんの立場だから、甘やかしちゃって大変なんだ(笑)。
水野:
むっちゃ甘やかしてるよね。
あかほり:
ところでさっきの話を聞いてたけど、白鳥君はツイッターとかの短い文章が上手じゃないか。短い文章を書けるってのは、すごく難しいことなんだぜ?
水野:
将棋のインタビューも面白いしね。取材がしっかりしてると思う。
──励ましていただいてありがとうございます……ただこの商売、いずれ必ず売れなくなる時が来ると思うんです。ヒット作を書いても、新作が売れる保証は全く無い。むしろそういう谷間は必ず来ると考えて、どうすればそこから這い上がることができるかを準備する必要があると思っています。
谷間と、長い下り坂
──そこで教えていただきたいのですが……あかほり先生は谷間を経験なさったじゃないですか。『セイバーマリオネット』が終わった頃から、ヒット作が出なくなった。昨日までと同じことをやっているはずなのに、受けない。なんで当たらないか全くわからない。『オタク成金』に詳しく書いてあって胸を抉られたのが、この部分なんです。
「実は、今回の『オタク成金』って、お金持ちになれてよかった……という部分を伝えたいんじゃなくて、金があっても、何もできないのが一番悲惨なんだってことも伝えたくてさ。
いくら金があったって、ヒット作はできないんだよ。こんなに金があるのに、俺、なんでヒット作が作れないんだ……って、長く作家をやってればわかるけど、それが作家として一番つらいところでね。金で集められる情報も状況もあるはずなのに、なんでヒットが作れないんだと」
ラノベの世界で谷底に突き落とされた先生は、漫画原作者として復活なさいますが……あかほり先生が谷間を抜けられたのは、なぜなんでしょう?
あかほり:
「企画を立てるぞ!」って気力はすごくあったんでね。何の企画も立てられない、何の話も書けない……ってなら、諦めたと思うんだよ。
「まだこういう作品をやりたい!」って気持ちはあって、そんなときに拾ってくれる人がいたから、その人とやったって感じかな。
けどそれは、俺が「この企画どうですか!?」って自分で持って行ったものじゃなかったんだ。
──え?
あかほり:
その救ってくれた編集さんに言われたのがね?「僕があかほりさんとやりたい企画の根本を考えるまではダメです」って。
──ああ……素敵な言葉ですね。本当にあかほり先生を谷から引き上げようとしてくれているのが伝わってきます……。
あかほり:
で、その人が「今度こういうのがやりたいんですけど、それについて企画あります?」と言ったときに、すぐ「じゃあこれどう?」と出せたんで。それが何とかなったんで、谷から戻ってこられたな。
今回の、歴史小説がダメだった後も……「やっぱ漫画原作でやってかないとな」と思って、いろんなとこにもういっぺん挨拶に行ったら「ちょうどよかった!」「今ここが空いてるんだけど!」ってお話をすごくいっぱい頂けたんで。
それで復活できたなって。けど悪い癖でね。「仕事を取りすぎてダメになる」ってのもあるんだ(笑)。
水野:
はたから見てると、あかほりは今、流れが来てますよ。作品力よりも企画力の時代が来てますよね。
ネット漫画の時代が来たでしょ? それって脚本家の経験が役に立つから。
あかほり:
けど、今はチーム制だよね。だって女子高生の会話なんて書けねーもん! だから弟子とかに「ちょっとここ書いてよ」ってお願いしてさ。
──脚本家さんって師弟関係があるじゃないですか。そこの人間関係の濃さって、今のラノベ作家には無いもので、羨ましいと感じます。
あかほり:
榊一郎とかも弟子いっぱい抱えてるじゃん! 俺が育てた人間の半分くらいはアニメの脚本を仕事にしてるけど、「いろんなことやりたい!」って人間がウチにはいっぱい来たかな。
──それから今日、水野先生におうかがいしたかったことに、『ど根性ガエルの娘』【※】のことがあるんです。あの漫画の5巻で、水野先生が作者の大月悠祐子先生に対して、いくつか印象的な言葉を投げかけるシーンがあって。大月先生の漫画が50万部を突破した、お祝いの席でのことなんですが……。
※『ど根性ガエルの娘』大月悠祐子(かなん)作。大月の父である漫画家・吉沢やすみの姿を通じてクリエーターの苦悩を描く自伝的漫画。
水野:
ああ、『ギャラクシーエンジェル』の頃にね。

──「デビュー作が売れるとつらい」という言葉がありましたよね? さらに「売れても売れなくてもやることは一緒」という言葉もありました。デビュー作が歴史的なヒット作になった水野先生が、どういう経緯でそういう心境に至ったのかを教えていただけませんか?
水野:
デビュー作が売れるとですね。要するに、作家人生が長期の下り坂なんですよ。
あかほり:
はっはっは!
水野:
僕はそれを自覚していたから、軟着陸させようと。墜落はしないでおこうと(笑)。
ゆ~っくりと、なだらかに……降下していこうと。途中からはそういった意識を持つようにはなりましたよね。
──決して超えられない壁を、自分で作ってしまった。そこを超えられないまま仕事を続けるというのは、我々では想像できないほどの苦悩だと思います。そんな苦悩を抱えたまま……死ぬまでラノベ作家であろうとする。あまりにも苦しすぎませんか?
水野:
本当は、過去の自分を超えたいという意識はあるんです。でも理想を持つと同時に、現実として「軟着陸をさせなければ」っていう意識を持つのは必要だから。じゃないと自分の心がね、保たないんですよ。
それがわかってるから、かなんちゃん……で、いいのかな。大月悠祐子さんね。
『ギャラクシーエンジェル』というのは、ブシロードの木谷会長がプロデュースされて。僕はそこに、最初はSF考証という形だったんですけど、最終的には総監修というプロデューサーのような形で入って。かなり大きく関わっていた。
──小説も書いておられますよね。アニメとは雰囲気が大きく違って、びっくりしましたが……。
水野:
僕自身のことよりも、チーム制だったので、チームのモチベーションを高めるということを考えた。かなんちゃんは若くて、野心的でもあったから……あんな大きなプロジェクトでキャラクターデザインと漫画を担当して、意識も高い。自信もあったと思います。コミックもすごい部数が出ましたからね。
あの企画は、かなんちゃんのキャラクターをいかに魅力的に見せるかというのが芯だった。だから神坂さんから教わった「女の子たちが輝くために」SF考証をしたんです。あの世界は女の子たちが気持ちよくなると高エネルギーが出るという設定で……(笑)。
──そうでしたね(笑)。
水野:
そんな設定を考えてる時点でSF考証としては負けかなと思うんですけど(苦笑)。
あかほり:
ふふふ。
水野:
それで、飲みの席で、伝えないといけないと思ったんでしょうね。自分が……つらかったから。最初に大きな成功をしてしまうと、次が失敗したとき、世界から掌を返されてしまうから。
彼女にとっては、僕からそんなことを言われたのが驚きだったと思うんです。言われた当時は理解できなかったんじゃないかな。ただ、現実にそうやって掌を返されることがあって、そこで「あのとき水野さんにそう言われたな」って思い出してくれて、漫画に書いてくれたんじゃないかな。
──水野先生ご自身も、掌を返された経験がおありなんですか?
水野:
やっぱりねー。露骨にありますよ、そりゃ。
けどそれは当たり前やと思いますよ。編集者って、これから伸びていく人が好きなんですよ。何でかって言うたら……「俺が育てた」って言いたいわけじゃないですか。
──もう育ってしまった人を担当しても、自分の評価に繋がらない。
水野:
「どうせ水野はなー。そこそこ部数は出るけどー」みたいに考える人が出てくるのは、仕方がないですよ。
でも僕は「俺のことを何だと思ってるんだ!」と怒るようなタイプじゃないから。逆に、それで僕が売れたら、編集者も喜ぶし……だから企画を育てていきたいって思っているんだけど。ただ……そうやって割り切れる人ばかりじゃないから。
──一般文芸の世界でも、そういう話を聞いたことがあります。直木賞を取ったら、その瞬間に人がサァァ……っと引いていくって。仕事は増えるけど、熱が消えると。
水野:
特に作家って、なんやかんや言ってもナイーブな人って多いから。僕だってそういう部分はあるし。かなんちゃんはそういう部分が大きかったから……忠告というよりも、励ます意味で言ったんだと思う。
失敗して、売れなくなる。企画も通りにくくなる。そんなときに足掻いたって仕方がない。「どうやったら売れるのか?」ということを考えつつ、自分の書きたいもの・書けるものを、書いていくしかない。
「書きたいもの」っていうのは同じ。それを「どうやったら売れるか?」と考えていく。だから「やることは同じ」なわけ。それを伝えたかったんじゃないですかね。でも、僕はそれよりも……。
──何でしょう?
水野:
彼女にセクハラをしなくてよかったな……と。
あかほり:
はははははは!!
──まさに水野先生がカッコイイことを言った直後のページで、セクハラする編集者が登場しますからね(笑)。

ネット小説とラノベ作家
──ラノベができる前のことから始まって、3時間近くもお話をうかがってきましたが……今って、先生方が台頭なさったラノベの黎明期に、すごく似てる部分があると思うんです。
あかほり:
ああ、それはあるかもね。
──たとえば、私の世代のラノベ作家って『連載』を経験してる人が極めて少ないんですよ。
あかほり:
そっか。今は雑誌って隔月で出てる『ドラゴンマガジン』だけなのか。
──『電撃文庫MAGAZINE』も『ザ・スニーカー』も休刊しました。でも今の子達は、ネットに自分で連載している。
水野:
それこそ毎日連載してるわけですからね。
──そしてそこで人気を獲得したものが書籍化され、メディアミックスされる。レーベルの力が支配的だった頃と比べて、レーベルが存在しなかった頃に戻ってるような印象を受けます。
水野:
それって圧倒的に正しいですよね。
──私もそう思います。新人賞システムは、それぞれの編集部が面白さにフィルターをかけていた。編集者の力量が高く、かつ作家が未熟であればそれも上手く行きますが……経年劣化によって、全てのレーベルにおいて編集部の意識の硬直化が起こりました。面白さの物差しが一つになってしまった結果、文庫のラノベは「全部似たような作品で、つまらない」という意識を持たれてしまった。
あかほり:
あと、今ってさぁ。作家とファンの子の距離がすげー近いよな。SNSを駆使して、ファンの子と交流して、作品のランキングを上げていくわけだろ?
──宣伝活動も作家に必要なスキルになっていますね。
水野:
これは以前、賀東招二さん【※】と話してたことなんですけど……「ラノベ作家ってラーメン屋に近い部分があるよな」と。
※賀東招二…… 『フルメタル・パニック!』『甘城ブリリアントパーク』作者。
──それはすごく面白い視点です! さすが賀東先生……。
水野:
ファンの意識と、ラーメン屋の店主の意識が、比較的近い。そしてファンの中に、将来的にはラーメン屋になりたいと思ってる人がけっこういる。「ああ、似てるよね」と。
──その点、あかほり先生は『ぽりりん新聞』をご自身で発行なさるなど、かなり早くからファンとの交流にも力を入れていらっしゃった印象です。
あかほり:
ファンクラブみたいなのはやりましたね。あんまり上手くいかなかったけど……。
──そうだったんですか?
あかほり:
ラジオとかもやって、敷居は低めにしたよね。でも……当時はまだ、「作家は友達じゃなくて偉い人」みたいな意識はあったような気もするな。
それに俺は低くし過ぎて失敗したかな、と思うこともあってね(苦笑)。
水野:
でも僕からすると、あかほりはアニメ畑の人間だから、そうやってラジオやったりして自己宣伝できるわけじゃないですか。それは「ズルいなー」と思ったりもしましたよ。
あかほり:
色が付き過ぎちゃったんだよね。それで後で困るんだ。で、ラノベを書く人たちも上手い人ばかりになって。俺からすると……難しいというか、本当に文字を書くのが好きな人たちのジャンルになってしまった。
──そうしてラノベは一時的には隆盛を誇りますが、どんどんニッチな世界になってしまった。まさに一部のラーメンの世界と同じように……。
あかほり:
そうなると、俺は企画が好きだから。だから漫画の連載のほうへ行ったんだよ。
で、漫画の連載に行ってからは、自分の色を隠そうとしたんだ。ペンネームをいっぱい使ってね。
──『あかほりさとる』というジャンルを封印なさったわけですね。なるほど……あかほり先生があまりメディアにご出演なさらなくなった理由が、ようやくわかりました。
多様性の時代を生き抜く
──黎明期から現在まで生き抜いてこられたお2人から、今のラノベ作家たちにメッセージをいただけませんか? とても貴重なものになると思うんです。今のような時代だからこそ。
あかほり:
正統派のほうは水野さんに任せるとして……作品作りをやってるなら、俺のように、ラノベでちょっと頭打ちかな? と思うようになっても、漫画原作とかあるから。
──ラノベだけ……というか、小説という表現だけにこだわるな、と。
あかほり:
作品を作るということをやめないで、さらに別の方向に行けるよ……ってことを、俺を見て、思ってほしいなって。
水野:
あかほりのほうが、ラノベ作家の人生というか、モデルケースになってるよね。
あかほり:
ははは! 実際、絵は描けるけどストーリーは作れないって人、いっぱいいるからね。ネット漫画もすごい数になってるじゃん。だから「物語を作って食っていくジャンルって、ラノベ以外にもいっぱいあるんだよ」ってことを、ラノベ作家のみんなにも知ってもらえたらね。
ほら、テレビのおかげでラノベ作家って儲かるって話になってたけど、さらに「息が長く続くぜ!」ってふうになるかもしれないからね。
それで新しくラノベ業界に入って来た連中が「ぜんぜん儲かんないし、つらいだけじゃん!」てなったら、テレビ局に文句言ってくれよな!

──ははははは! 水野先生はいかがですか?
水野:
僕は今、最前線で書いてる人たちと交流があるわけじゃないけど……小説投稿系のサイトで人気が出て書籍化される、コミカライズもされる。ある意味、売れ方というか、売れる方法論って確立されてるじゃないですか。そういうところで力を発揮できる人にとっては、今はチャンスだと思いますよ。
──新人賞システムは崩壊しましたけど、だからこそ裾野は広がっている印象があります。
水野:
そうそう。どうやって売れるかについては、ネットで投稿してる人たちのほうがノウハウを持っている。売れているものに照準を合わせつつ、次に来るものもチェックする。そしてダメなやつは即、潰して。新しい企画をやる。
ただ、人が増えているから、競争は激しいと思う。その競争に打ち勝てば、楽して大儲け……という世界が待ってるんじゃないかな。最初の8000万円に話に繋がるけど。
──綺麗にまとめていただいて、ありがとうございます! ええと、最後にドワンゴの竹中さんから質問がありまして。水野先生になんですが。
水野:
はいはい。どうぞ。
──「エルフのスタイルって、今、巨乳か貧乳かで派閥がわかれてるんですが、水野先生は日本のエルフを作った際に、どちらを意識されましたか?」と。何だこの質問……。
水野:
僕自身は「天は乳の上に乳を作らず」という立場で、全ての乳は尊いという立場です。

あかほり:
何だよそれは(苦笑)。
水野:
至高なものなので、上下を作れるはずがないではないか。ただエルフに関しては、出渕さんが描いたもののイメージだと思うんですよ。
で、出渕さんは松本零士先生の女性キャラが大好きなんですよね。だから、割と細い感じで描かれたというのがありますね。
──メーテルなんですね。日本のエルフは。
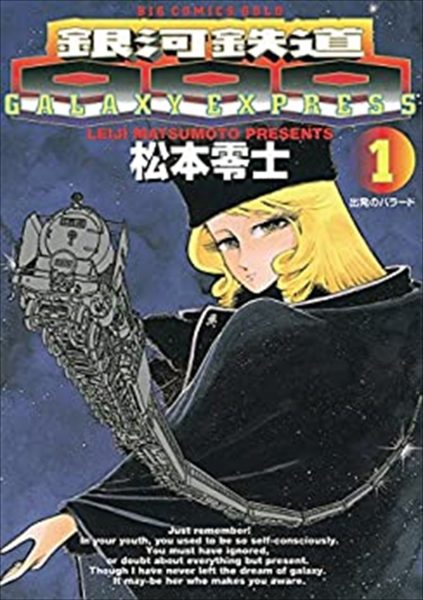
水野:
でも、それだけじゃあ……というのがあって、ダークエルフのほうはグラマラスにしましょうと。アニメのOVAで、対になるようなキャラとして登場させた。それでダークエルフは巨乳という伝統だけが、なぜか業界のミームとして残っているのかなと(苦笑)。
──じゃあエルフがエッチなのはやっぱり水野先生が元凶なんじゃないですか(笑)。
水野:
最近は、村を焼かれたり、奴隷にされたり。「エルフ受難やなぁ……」と思いますよ。
あかほり:
受難だよね。
水野:
いうて僕も、どの作品にもエルフっぽいものを出してますから。歴史的に見ても、エルフ的なものとの異種婚姻譚は、多いんです。つまり……。
──つまり?
水野:
人間的な異種族を見たらヤリたいという男は、昔から多かったということでしょう。そういう中二的な……ヴァルキリーとは子供が生まれたり、ニンフもたくさん子供を産んだり。もともとエロいものなんですよ。『指輪物語』では高貴な種族として描かれ過ぎていますが、本来のエルフはもっと淫靡なものだし、コケティッシュなものでもある。
だから……今のエルフ像は多様性があっていいなぁ、としか言いようがない。
あかほり:
ははははは!
水野:
しかし僕は『指輪物語』に対してリスペクトがあるので、ロードスに出てきたエルフは高貴で、細いんです。
──エルフの話はしなくていいと言ってましたけど、最後は結局エルフの話題になりましたね(笑)。本日はありがとうございました!
……この対談からおよそ2週間後。
あかほりと水野を慕う後輩作家たちがオンライン飲み会を開いた。
対談でも陽気だったあかほりだが、飲み会でもそれは変わらない。いつ、どんな場でも、誰が相手でも、あかほりさとるはあかほりさとるだ。
「よう白鳥君! この前は楽しかったぜ!」
ラノベ作家達を前にして、あかほりは何度もそう言ってくれた……それを単なる挨拶ではなく、私がこの企画を続けられるよう協力してくれているように思うのは、考えすぎだろうか?
そして、あかほりは誰よりも先に退室した。4年前の、あの夜のように。
再び多くの仕事を抱えるようになった今、疲れこそあれ、その表情は終始晴れやかだった。
参加者の一人である宮沢龍生【※】は、私があかほりと水野の対談記事を書いていると知ると、言葉が止まらなくなった。
※宮沢龍生……『インフィニティ・ゼロ』『いぬかみっ!』(有沢まみず名義)作者。
「あかほり先生のお弟子さんたちが集まる忘年会に参加させていただいたときに、驚いたことがあるんです。先生はお弟子さんに『お前これ好きだよな?』『お前はこれが好きだったよな?』って、料理をずっと取り分けてるんです」
「原稿を全没にされたときも、あかほり先生はぜんぜん怒らないんです。全没ですよ? 普通なら怒り狂うのに、ケロッとしてこう言うんですよ。『だって面白いものを書きたいじゃん!』って」
「すごいなと思って。でも……照れがあるんでしょうね。『見習うなら水野さんにしろよ』と、いつも言われました」
そんな宮沢に対抗するかのように、酒が入った水野も、あかほりについて語り始めた。
「あかほりの前にあかほりはいない。あかほりの後にもあかほりはいない」
何度も何度も谷底から這い上がり、時代の寵児になる盟友のことを、水野はそう表現して讃える。
求められるものをベストなタイミングで提供できるという稀有なその才能を、水野は対談の中でも認めている。
しかし水野は同時に、あかほりの中にずっと存在するコンプレックスも見抜いていた。
あかほりが本当になりたいものは、企画屋でも編集者でもアレンジャーでもないと。
「あかほりさとるは、クリエーターとして戦って評価されたいんだよ!」
後輩たちに熱くそう語る水野もまた、クリエーターとしての壁に突き当たっている。
ロードス島戦記の最新シリーズである『誓約の宝冠』は、この対談の中で水野自身が語っているように、1巻で止まってしまっている。
その1巻は、掛け値なしの名作だった。
読んだとき、あまりの志の高さに震えた。水野はこの新シリーズで明らかに世界を狙い、そしてロードスという作品に普遍性を与えようとしていた。ロードスを……いや、ライトノベルというジャンルを、いつの時代の、どこの国の人々にとっても楽しめる存在へと押し上げようとしていた。
自分の作家人生を『長い下り坂』と語っていた男は、自分自身の築いた高い壁に阻まれ、前に進めなくなってしまったのだろうか?
しかし対談の中で水野はこう言っている。
「今は止まってしまっている」……と。「今は」と。
ならば我々は待つだけである。
完結するかはわからないが、水野は必ず続きを書く。
なぜなら水野良は、ラノベ作家として死ぬのだから。
あかほりさとると水野良。
2人は今も後輩たちに道を作り続けている。
それはメディアミックスや、ライトノベル以外の活躍の場を開拓するという意味だけではない。それだけならば私は今の2人に話を聞こうとは思わなかっただろう……過去にいくらでもそのことについて語った記事は存在する。
私は見せたかったのだ。ラノベ作家という職業を作った、2人の男の今を。過去の『栄光』でも『成功』でもなく。
『苦悩』という、戦い続ける背中を。
(了)

