ハリウッドが「同性愛」を認めるまでの歴史を5分で解説してみた――『ムーンライト』が『ラ・ラ・ランド』を押しのけてアカデミー賞を獲った理由
ニューシネマ時代の到来で花開いた「LGBTムービー」は、80年代で停滞期を迎える
松崎:
60年代のヘイズ・コードが廃止されたウラにあったのが『俺たちに明日はない』という映画です。アメリカン・ニューシネマというものが始まったんですね。ヌーヴェルヴァーグというフランスでの映画の革命があって、それに影響されてアメリカの人たちがヌーヴェルヴァーグっぽい映画の表現を始めたのが「アメリカン・ニューシネマ」と呼ばれています。
それの一番最初の作品ではないかと言われているのが1976年の『明日に向かって撃て』です。暴力、セックス、芸術。当時の人たちが見たら革新的だったんです。

松崎:
「映画の表現はこういうふうにしたほうがいいんじゃないのか」という声が強くなってきたんですね。そういうことでヘイズ・コードがなくなって、「15歳以上ではないと見られません」というレーティングというものに変わっていったんです。
このアメリカン・ニューシネマも特徴があって、アカデミー賞を取った『真夜中のカーボーイ』というものがあって、ニューシネマは男の二人組が旅をしてというものが多いのですが、男同士の恋愛ものとして楽しんでいた人もいた。
とくに『真夜中のパーティ』という映画は「ゲイムービーの古典だ」と言われるくらい、ゲイの人たちの話です。ゲイの人たちが真夜中にアパートに集まって話し合うという映画です。もともとは舞台劇だったのですが、ここに出ている役者自体がそういう世界からやってきた人もいる。そして役者の半分はエイズで亡くなっているんです。
ということで、「ゲイの人たちがいる」ということを描けるようになったのが1970年代というお話でした。

松崎:
ところが1980年代になって停滞してしまいます。『ビバリーヒルズ・コップ』の中で、ゲイをコメディとして描いているシーンがありました。ゲイであることをなじったりするのがトレンドになっていました。
先ほど紹介した『真夜中のパーティ』の監督が『クルージング』という映画を作ったんですが、これはハードゲイの世界の映画で、あまりにも興味本位だと言われて上映禁止運動が起こる騒動になってしまったんです。『真夜中のパーティ』で天井を破ったはずなのに、もとに戻ってしまった。
それでも80年代、多少の兆しがあって『ハーヴェイ・ミルク』という、2008年にショーン・ペンが主演した『ミルク』の実際のドキュメンタリー映画です。これが1984年のアカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞に輝いんたんです。ゲイであることを公言して、権利を主張しながら政治家として活躍したけれども凶弾に倒れてしまったというものです。
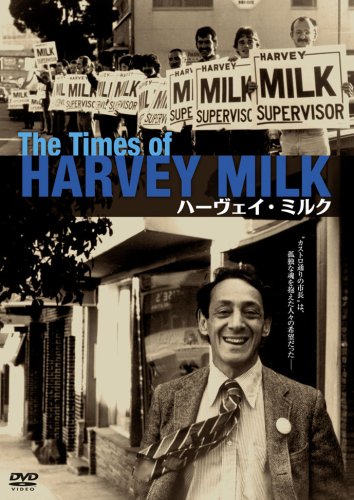
松崎:
そして翌年のアカデミー主演男優賞では『蜘蛛女のキス』という女装をしている人が主人公の作品ということで、演技賞としての初めてジェンダーに関する受賞だったと思います。90年代になると『テルマ&ルイーズ』という同性愛のことも絡ませているんじゃないかと後年評価された作品が現れました。
ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(監督賞)を取った映画の『乙女の祈り』という、二人の少女の友情も同性愛的な要素があるんじゃないかと評価されています。
あとは『ロングタイム・コンパニオン』という作品があったんですね。「ゲイコミュニティ」と「エイズ」という題材を初めて映画で扱ったものと言われていて、ゴールデングローブ賞で助演男優賞を取ったんです。あとは『クライング・ゲーム』だったり賞レースにかかってくるような作品が増えてきました。それが90年代の前半です。
『フィラデルフィア』のトム・ハンクスに主演男優賞を与えたアカデミー賞の功績
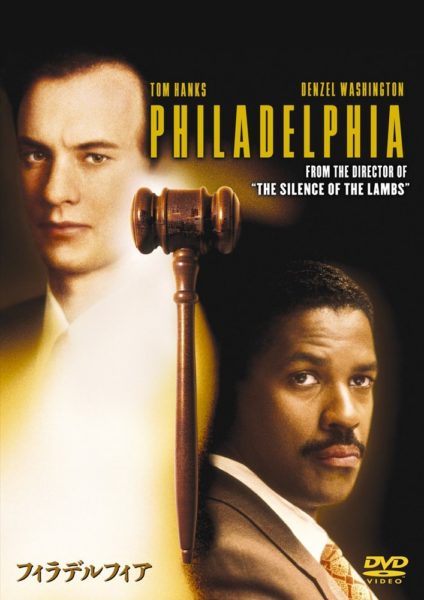
中井:
疑問に思ったのですがアカデミー賞は僕はコンサバ【※】なイメージがあるのですが、より同性愛に理解があったということですか。
※コンサバ
「コンサバティブ」の略。保守的な思想や考え方、スタイルなどを指す表現。
松崎:
93年にある映画が公開されたことが、第一の突破口になったと思うんです。それがトム・ハンクスが主演した『フィラデルフィア』ですね。この作品の前まで、トム・ハンクスってコメディ俳優でしかなかったんです。これがほぼほぼ最初のシリアスな演技なんです。
トム・ハンクスは本当にシリアスな役ができるのか? と言われていた。しかもメジャーな映画会社がエイズを題材にして、主人公の弁護士は同性愛者だと公言している。もしこの映画がコケたらトム・ハンクスのキャリアもダメになるけれど、ハリウッドも「エイズ」という言葉も映画の中で使えないんじゃないかと言われていた。
結果的にはこの映画はトム・ハンクスが主演男優賞を取ったことによって、エイズを映画の中で使うことがオッケーになった。そういう意味ではすごく功績があります。
スタッフ:
アカデミー賞にお墨付きをもらったということですもんね。
松崎:
僕がアカデミー賞に意味があると思うのは、仲間内で「これはいいよね?」という確認にもなる。映画の中で描くことが変わっていくきっかけになるんです。だから「この映画は面白いね」ではなくて、この映画が作られたことによって、表現が変わっていってタブーが消えたことのほうが重要なんです。
ちょっとここでアメリカのテレビの話をしたいのですが、テレビドラマで『エンジェルス・イン・アメリカ』というものがあります。これもゴールデングローブ賞で賞を独占しています。このころからテレビの世界では認められた。映画の題材にしてもいいんじゃないかとなったのが2000年の前半。そのときに出てきた映画が『ブロークバック・マウンテン』。
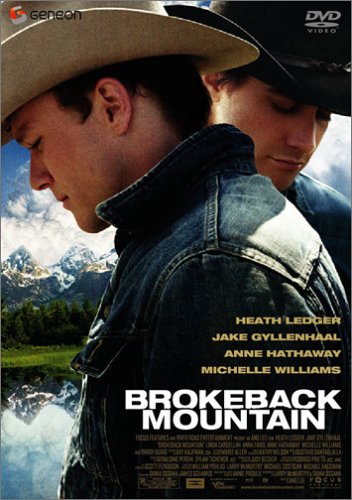
スタッフ:
名作ですね。
松崎:
アカデミー賞でこの作品は「作品賞を取るだろう」とみんな言っていた。LGBTがついにハリウッドで認められ、メジャーで解禁になるんじゃないかと見られていたのですが、最後の最後で『クラッシュ』という映画が名前を呼ばれた。
やっぱりアカデミー賞の会員は保守的な人が多くて、「やっぱりまだハリウッドで賞賛するのは早いんじゃないか」とう判断でした。このあと失速していくんですね。ハリウッドではなかなかうまくいかなくて、2013年に『ダラス・バイヤーズクラブ』という映画が扉を開きました。

松崎:
マシュー・マコノヒーとジャレット・レトが主演男優賞、助演男優賞を取った。この受賞まで2008年以降何年も、作品賞や役者部門でLGBTと思わしき役を演じた俳優やその作品は、候補にすらなっていなかったんです。
このあと、『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』で、ベネディクト・カンバーバッチが「ゲイじゃないか」と思わせる役を演じたり、『キャロル』や『リリーのすべて』が出てきた。
とくに『キャロル』はすごいな思ったことがあって、主演のケイト・ブランシェットが「今回はアカデミー賞は無理だと思います。でも10年前だったらこういう映画はノミネートすらされなかったので、誇りに思います」と言っていて、すごいなと思ったんです。
『ムーンライト』が作品賞を受賞。LGBT映画の今後の展望は?
松崎:
そして今年のアカデミー賞は『ムーンライト』が取ったじゃないですか。黒人のことを描いた映画でもあって、黒人の中の同性愛者を描いた映画ということで、これは『ラ・ラ・ランド』と比較したときに興行収入を見ると、やはり『ラ・ラ・ランド』のほうが見やすいと思うんです。
でもこの映画に意味があるのが、黒人の問題、貧困の問題、LGBTの問題もやっとハリウッドが認めたスタートラインだと思うんです。

松崎:
映画が始まった1895年から100年経って、やっとこういうものが作品賞になったことを起点にしておそらくこれからメジャー映画会社もこういう作品を送り込んでくるんじゃないかなと僕は見ています。そして今の世界的なトレンドとして別のものが出てきたと思っています。
シャーリーズ・セロンが主演している『アトミック・ブロンド』、ハル・ベリーが出ている『チェイサー』、アン・ハサウェイが出ている『シンクロナイズドモンスター』。この三本に共通があって、主演女優がみんなアカデミー賞を取っている。
あとは、この女優たちが制作に加わっているんです。つまり、「自分が出たい映画」として作った映画なんです。アメリカの役者は、レオナルドディカプリオだったり、ブラッド・ピットだったり自分が出たい映画がないから、自分で作るという動きがあります。
この三本の映画に話を戻すと、全部「男なんかいらない」というのが共通してあるテーマなんですよ。女性が強いということだけではなくて、女性の視点からも描きましょうということに今後なっていくんじゃないかなと思います。

松崎:
ですから点ではなく線で見ていくと、LGBTも流れの中で格闘しながら今やっと『ムーンライト』にたどり着いたということを念頭に、この映画を見ると、より「社会が同性愛をどう描いてきたのか」というものがわかると思いますよ。
―関連記事―
アニメの水着回・温泉回って実際テコ入れになっているの? ニコ生視聴者データを元に分析してみた
「『シン・ゴジラ』は東宝への宣戦布告」――庵野秀明に影響を与えた戦争映画の巨匠・岡本喜八を映画評論家が解説