『ブレードランナー 2049』ネタバレ気にせず徹底解剖 「この映画は、キリスト教などの宗教に対する強烈な問題提起が入っている映画なんだ」
二人の主人公の間に隠されたテーマ
岡田:
1982年に公開された元の『ブレードランナー』において、主人公のデッカードというのは、レイチェルという女が本物の人間であろうがレプリカントであろうが関係なく、自分の命をかけて救い出すというところを見せた。だからこそ彼は映画のヒーロー足り得るわけだ。
でも今回の主人公はそうじゃない。彼にもジョイというバーチャルリアリティの恋人が部屋にいて、Kがピンチに陥ったときに彼をかばうんだ。そのせいで、コントローラーみたいなものを踏みつぶされたジョイは消えてしまう。つまりバーチャルリアリティにすぎない、自分よりもはるかに偽物の命であるはずのジョイが自分の命を投げ出してかばってくれたのに、K自身はジョイのためになにもしてやれなかった。

岡田:
その後、心破れてロサンゼルスに帰ってきたとき、Kは巨大なビルボードにバーチャルリアリティの広告塔として映し出されていたジョイの別バージョンの子に声をかけられる。そのシーンは自分だけのフィギュアだと思っていたら、すごい大きなポスターが貼られているのを見て、そこら中で売られてることに改めて気がつくみたいな感じで、ジョイはなんだかんだ言っても量産品なんだ。
これは言っていたわけではないんだけど、Kはそこで俺が愛したつもりになっていた女もやっぱり偽物だったんだなみたいな気持ちになってしまう。
つまりあくまでも自分や恋人が本物か偽物かにこだわってしまうKと、自分が飼っている犬ですら本物か偽物かを問わないデッカード。この2人には、キャラクターとしての対立があるんだ。でも本編では、そのあたりの違いをギャップとして上手く描いていない。この映画で描こうとしているのは、Kという翼を失ってしまった天使の贖罪なんだ。
命をかけて自分を救ってくれたジョイの愛情を信じることができずに、俺もあいつも偽物だと考えてしまった彼は、おそらく堕天使なんだよ。堕天使としてのKが、贖罪のために信じるデッカードを命をかけて助けるという構造になっている。そしてKが堕天使であるように、本物の救世主というのもこの映画の中には存在している。それがデッカードとレイチェルの娘だ。
この娘はレプリカントの記憶を扱う博士に成長して、いろんな記憶を作って移植してあげることを通じて彼らを救っている。記憶を与えることで、レプリカントがレプリカントとして生きるうえでの”よすが”、しがみつける最後の生命線を作ってあげていた。

岡田:
これはキリストを見たとか、神の存在を確認したという信仰体験を持つことでたしかなと信仰心を持つことができるというキリスト教徒のメタファーであり、『ブレードランナー 2049』は、キリスト教などの宗教に対する強烈な問題提起が入っている映画なんだ。
Kが脇腹を刺されるシーンもスティグマータ【※】だと思うし、そういったいいシーンは本当にいっぱいあって、ストーリーだけを分解して話すといろんな要素が上手く噛み合わさっているように見えるけれども、作中では主人公Kの感情曲線がよくわからないまま、3時間近い尺で見せているから捉えどころがない映画になっている。だから、話の構造や伏線だけならきれいに組み合わさっているのに、その順番でだらだらと見せるなと思ったわけだ(笑)。
※スティグマータ(stigmata)
聖痕、イエス・キリストが磔刑となった際についたとされる傷。ここでは贖罪の視覚的なメタファーとして語られている。
『ブレードランナー 2049』を面白くするための3つの方法
岡田:
この映画をどうやったら面白くできるのか? 『ブレードランナー2049』は失敗作というよりも、ほんのちょっと変更を加えるだけですごく面白くなると僕は思っている。まず1つ目として、この映画の一番の問題は主人公がなにを考えてるのかわからないということなんだけど、こういう場合は前作の劇場公開版『ブレードランナー』でやったように主人公のモノローグを入れてしまえばいい。
「俺の名はK。レプリカントでブレードランナーだ。今から俺は自分の仲間を殺しに行く」、「汚い仕事をする汚い存在、それが俺だ。そんな俺でも家で待ってくれている女がいる。バーチャルリアリティのジョイだ。まるで30年前の日本のオタクみたいだって? こんな時代、男はみんなオタクでなければ生きていけないんだ」、「俺はジョイの偽物の笑顔に癒される。偽の笑顔に偽のキス。俺だって偽物、レプリカントだ」

岡田:
ナレーションを要所で入れたとしても、映画の進行上はまったく問題ない。むしろテーマ性がはっきりする。デッカードが生きていることを知らされるときにも、「デッカード? だれでも知っている伝説のブレードランナーで裏切り者だ。レプリカントと逃げた男。そしておそらく俺の親父だ」というセリフを入れるとわかりやすくなる。予算をかけたハリウッド映画なんだから、もう少しわかるように作るべきだ(笑)。
たしかにナレーションを入れれば、映像芸術性は下がる。だけどその代わり、大衆性はものすごく上がる。悪いことは言わない、試しにライアン・ゴズリングにナレーションをさせ、ダラスとサンディエゴで試写にかけてみればいい。みんな絶対にこっちのほうがいいと言うから。
芸術性が高いバージョンは、その後でファイナルカット版として作ればいいんだ。2つ目の改善点はヴァンゲリスの音楽をもっと使うこと。言い方は悪いんだけど、『ブレードランナー 2049』の中でかかる音楽に名曲がない。Kが死ぬシーンやとりあえず印象に残るような名場面では、昔の『ブレードランナー』と同じヴァンゲリスの音楽がかかってる。
このヴァンゲリスが流れ始めると、もう、映画館でもわかるほどにお客さんの背筋が一斉に伸びるんだ。ここはいいところだとわかる感じになっている。であればもう全部ヴァンゲリスでいい。ヴァンゲリスというのはシンセサイザー作家なんだけれども、今まで『炎のランナー』と『ブレードランナー』という2つの映画に音楽を提供している。この2作の音楽はどちらもシンセで作っているわりにはメロディーを中心に据えたセンチメンタルな曲なんだ。
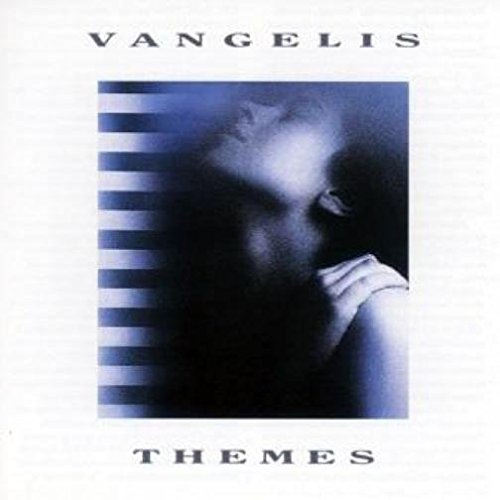
岡田:
そもそもの問題として『ブレードランナー 2049』では、そういうセンチメンタルな曲をほとんど流していない。普通のハリウッド映画というのは、盛り上がるところでは心臓がどきどきするような音楽をかけるものであり、アクションシーンであれば激しいギターリフレインが入っているような曲を入れるものだ。そのように見ているお客さんの感情をシーンに合わせて誘導するような曲の使い方をするものだけれども、『ブレードランナー 2049』は映像もアートぶっていて、音楽もアートぶっているから余計にわかりにくくなっている。
このままでは見ているシーンが悲しいシーンなのか、ドキドキするシーンなのかわからないままだ。ここに、ヴァンゲリスの音楽のようなノスタルジックでセンチメンタルなメロディーがあれば、今はどういう気分になればいいのかお客さんをちゃんと誘導することができる。そのほうが絶対いいと思うんだ。
3つ目にして最大の変更点は、ラストはKとジョイが2人でスピナーで去っていくというハッピーエンドにすること。なぜかというと、この2時間47分もある映画を見たお客さんには”ご褒美”が必要なんだ。フルコースの料理には、必ず最後にデザートがつくものだろう? これが1時間ちょっとで終わる一品料理みたいな映画であればどんな無茶をしてもいいけど、ハッピーエンドというのはその映画が当たるか外れるかを決める要素のひとつという以上に、制作者側から観客への”詫び状”でもある。

岡田:
長々としんどい話をしたけれど、とりあえず笑顔で終わりますよというのが、大衆演芸の世界では大事だと思うんだ。そこで与えられる“ご褒美”が雪を見ながら死にゆくKの口角がうっすら上がっているというだけでは、僕らは安心して家に帰れない(笑)。
Kとジョイが駆け落ちするラストで生まれる意味
岡田:
ラストシーンについてもう少し真面目な話をするならば、ジョイとKが最後に駆け落ちすることでこの映画はようやくリドリー・スコットの支配から逃れられると思う。リドリー・スコットの世界観におけるレプリカントというのは、例外なく”逆フランケンシュタイン・コンプレックス”というのにかかっている。
フランケンシュタイン・コンプレックスというのは、アイザック・アシモフというSF作家が、戦後すぐに書いた小説の中で作った言葉で、人間が作ったロボットなどというものを神が許すはずがない。ゆえにロボットは人間に反乱するに決まっているという偏見を意味するものだ。リドリー・スコットの世界では、この逆のコンプレックスが蔓延している。
『ブレードランナー』シリーズにおけるレプリカント、もしくは『エイリアン』シリーズのアンドロイドはなぜか必ず人間に憧れており、人間になりたくて仕方がないというコンプレックスを持っている。なので、『エイリアン:コヴェナント』に出てくるデイヴィットも新しい生命を作って人間のまねごとを始めてしまう。この”逆フランケンシュタイン・コンプレックス”がある限り、あくまでもリドリー・スコットの世界観になってしまうんだ。

岡田:
ところが、『ブレードランナー 2049』のラストシーンを、Kとジョイが駆け落ちするというふうに変えるだけで話がぜんぜん違ってくる。前作の劇場公開版『ブレードランナー』のラストで見せたデッカードとレイチェルの駆け落ちというのは、キリスト教徒からすれば神に祝福された人間と、祝福されていないレプリカントが駆け落ちして、果たしてそこに幸福があるんだろうかというちょっとショックな出来事だった。
レプリカントのKとバーチャルリアリティのジョイの駆け落ちというラストは、俺たちは創造主なんて必要としないというような明確なメッセージにもなり、またキリスト教徒にしてみるとエデンの東の向こう、別の大陸に移住するくらいの大事件となるわけだ。
ラストシーンでKのモノローグとして、「俺は人間の偽物、レプリカント。ジョイは生命の偽物、単なるプログラム。俺たちの間に愛はあるだろうか? それはわからない。幸せな日々があればそれでいいのだ」みたいなことを言わせておけば、前作が持っているショック性より更に上のショックを与えることができたはずだ。これはキリスト教的なショックなんだけども、たぶんこれでも人は感動するし、言いたいことは伝わる。
なにより、こうした方が、リドリー・スコットの”レプリカント”として作った映画ではなく、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督自身の映画になったと思う。今のバージョンだと、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督がリドリー・スコットが作りたかったことを忖度して作っちゃってるように見えるんだ。新しいシーンを撮影しているような時間とか予算がないのであれば、デッカードを助けるために死にゆくKが見た幻というラストシーンでもいい。
例えば『フランダースの犬』のラストでも、死にゆくネロが「やっとルーベンスの絵が見れたよ、パトラッシュ」とつぶやくと、天使が迎えにきてくれる。現実的にはなにもいいことなんて起きていないけれども、あれを見て感動するだろう? これによってネロの正しさが認められた気になるから、だれかに認められたというのがないと人間の心というのは不安定になる。
だからラストは、人間とレプリカント、最後の希望の象徴であるデッカードとその娘を天から見下ろすKで、その横でジョイが微笑んでいたら、もうそれだけでいい。そのほうが『メッセージ』を撮ったドゥニ監督らしい映画になっていた。そういうラストだったとしてもヴァンゲリスの音楽で終わっていれば、だれも文句を言わない。なにより、『ブレードランナー 2049』のテーマに近いと思うんだ。
―人気記事―
ヒャッハァァァー!! 『マッドマックス』の魅力に憑りつかれた“ファンキーな人々”が集まるフェスが激アツだった【画像70枚】
「AIは魂を持つのか? ゴーストが宿るのか?」押井守(映画監督)×山田胡瓜(漫画家・『AIの遺電子』作者)特別対談
関連動画