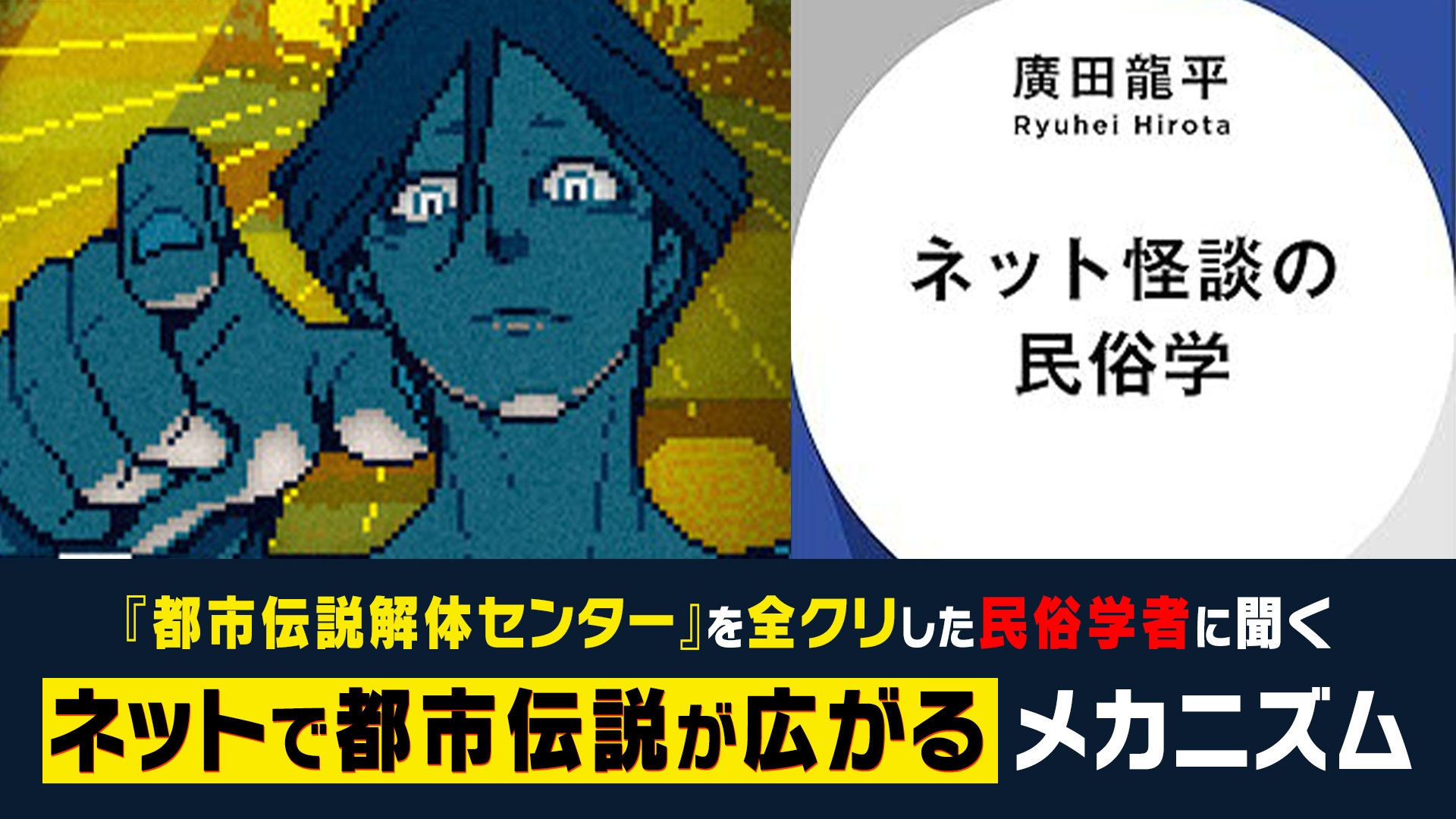【ネタバレ注意】『都市伝説解体センター』を全クリした民俗学者が語る“ゲームと異界”――「くねくね」も「因習村」も「きさらぎ駅」も、流行った理由は「異界」にあり!【『ネット怪談の民俗学』著者 廣田龍平インタビュー】
記事の要約
■『ネット怪談の民俗学』の著者に『都市伝説解体センター』を遊んでもらった
・『都市伝説解体センター』は、累計30万本以上を売り上げた人気アドベンチャーゲームです。
・SNSを使った調査システムが特徴で、都市伝説の真実に迫る高い没入感が魅力です。
・民俗学者、廣田龍平さんはゲーム内のSNS描写のリアルさや、都市伝説が不安から生まれる背景を評価しました。
■『都市伝説解体センター』と民俗学の違い……「解体」は“しない”
・ゲームのSNS拡散と現実は異なり、現実ではごく少数のアカウントがリポストで噂を広めます。
・民俗学者は真相究明や「解体」はせず、噂の時代背景や人々の行動変化を調査します。
・都市伝説は、社会の漠然とした不安が具体的な物語として形になったものだとも言え、「モラルパニック」と関連しています。
■『都市伝説解体センター』でも描かれた噂の魔力……「ネットの闇」と「モラルパニック」
・「モラルパニック」は特定の集団や架空の存在を悪者にして起こる現象で、現代に限らず昔から存在します。
・「スレンダーマン」を信じた少女が起こした事件のように、創作が現実の事件を引き起こす例もあります。
・デマを止めるには、大元の投稿を削除したり、テレビなどの強力なメディアが特集を組んだりするしかないとされています。
■『都市伝説解体センター』から語る「境界」の民俗学
・廣田さんは『都市伝説解体センター』の「異界」のストーリーでの、「境界」という概念の描写に注目しました。
・「境界」とは、昼から夜へ、子供から大人へといった「ある状態から別の状態へ変わる際の境目」という普遍的な概念です。
・「きさらぎ駅」や「ドッペルゲンガー」などの都市伝説も、この「境界」の概念が反映されているとも解釈できます。
■ネット怪談の特徴、都市伝説や伝承との違いは?
・ネット怪談は拡散速度が速く、画像や音声を含むマルチメディア形式で展開されるのが特徴です。
・従来の都市伝説と異なり、元ネタをたどりやすいため、ある意味では真相の究明が可能です。
・2000年代には、「都会から離れた田舎にヤバいものがある」といった因習系の物語が流行し、これも「境界」の概念と紐づけられます。